
|
4 成果と課題
たいへん楽しい活動です。子どもたちは嬉々として校内を走り回り、次々と目標物を探し出していました。ビンゴの用紙に記入している時から、「これはあそこにあるぞ」とか「あったっけなあー」などのつぶやきが聞こえ、校内の自然に目を向けるには適したプログラムであると考えます。
今回の実践では、単にフィールドビンゴを楽しむだけでなく、「ふりかえり」や「わかちあい」をどのように行うかも多少考えてみました。ここでのふりかえりの視点は、次の2点です。
?@学校内の環境に対するふりかえり
?Aフィールドビンゴを行ってみての発見、気づきに対するふりかえり
?Aの活動を行っての発見、気づきに対するふりかえりは、活動の終末(前項の?D)に個々の感想を発表させたことと、その後で感想を書かせたことで行いました。
感想は後で印刷し全員に配り、話し合いを行いました。また、ここでのわかちあいの手立ては次の2点です。
?@活動をグループで行わせたこと
?A活動を行った後の感想の発表と感想をもとにした話し合いを行ったこと
?@については活動を少し難しくしようという意図もありましたが、思わぬ効果がありました。何かを見つけたときにはそれをグループの友だちに紹介しなくてはいけないからです。つまり、自分の発見を友だちとわかちあうことができたわけです。「○○君が教えてくれたので初めて見つけられた」という子どもがずいぶんといましたし、「みんなで探すことが楽しい」と発言した子どももいました。
また、?Aの感想をもとにした話し合いでは、「サンショウの葉のにおい」や「とげのある葉が難しかった」ことなどに共感する子どもがたくさんいて、もう一度見に行こうという話し合いになりました。実践では、この活動の後、「においのする葉」に焦点を当て、いろいろなにおいのする葉を探す活動、そして「ぼくの木、わたしの木」の選定と継続観察を行いました。「ぼくの木、わたしの木」を選ぶ視床として「におい」を理由に選んだ子どもは30名中21名おりましたので、樹木に対する視野を広げることができたと考えます。
このような活動は、年間を通じて何回か繰り返す必要があるでしょう。そのための指導時間の確保がなかなか難しいのですが、子どもにとって必要だと思うこと一は理科や学級活動などの年間計画の中に組み入れていく必要があると考えます。
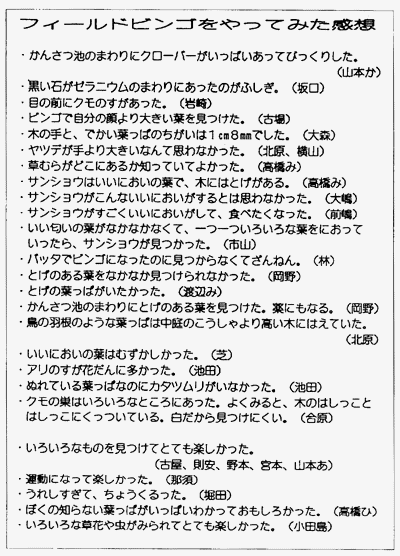
前ページ 目次へ 次ページ
|

|